北方史参考書
加藤九祚/著『シベリア記 遥かなる旅の原点』 論創社 (2020/8)
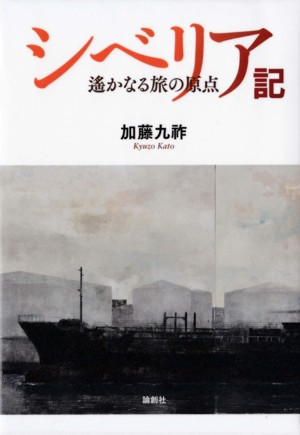 著者の故・加藤九祚先生は、国立民族学博物館教授などを務めた、文化人類学者で、日本のシベリア・中央アジア研究の基礎をつくった人。2016年、ウズベキスタンで発掘調査中に倒れ、現地の病院で死去した。シベリア抑留の経験があり、この関係でシベリア研究者となった。
著者の故・加藤九祚先生は、国立民族学博物館教授などを務めた、文化人類学者で、日本のシベリア・中央アジア研究の基礎をつくった人。2016年、ウズベキスタンで発掘調査中に倒れ、現地の病院で死去した。シベリア抑留の経験があり、この関係でシベリア研究者となった。
同名の本が1980年3月、潮出版社から出版されている。本書は、潮出版社本に掲載された論文が中心になっている。
本書の内容は、シベリアと日本の関係が記述の中心になっている。革命前にウラジオストックに進出していた日本人の話や、シベリア出兵の話、それから、著者自身のシベリア抑留体験など。
シベリア出兵の時の日本軍の残虐行為はロシアでは有名な話だが、日本ではあまり知られていないようだ。本書にはこの点について若干触れられている。
例えば、(1918年)九月十九日、野瀬工兵中佐の率いる一個大隊の進駐したブラゴベシチェンスクの状況について石光真清は書いている。石光はこの都市で特務活動に従事していたが、日本兵から暴行されたというロシア人からの訴えが絶えなかった。「早速、事務所の者に調査させると大体において事実間違いなかった。市内各所に同じような事件が起こっており、私に直接訴えて来ぬものはその一部分であって、大部分の被害者は日本軍の報復を恐れて泣寝入りしているのであった」(『誰のために』昭和43年・龍星閣刊、二六〇ぺージ)
こうした状況は各地における武力衝突ともからんで、しだいに疑心暗鬼と憎悪を増幅し、ニコラエフスク事件(尼港事件)のような数々の不幸な事件が生まれた。兵隊は、「殺さなければ殺される」というような心理状態におちいる。後に『岩波ロシア語辞典」の著者となった八杉貞利は一九二〇年(大正九)沿海州を旅行し、当時の見聞を日記に書き残している。八月十三日、ウスリー鉄道のシマコーフカ駅付近でのこと。日本軍の一少尉が視察にきた某少佐につぎのようなことを説明していた。
「……目下も列車には常に過激派の密偵あり、列車着すれば第一に降り来り注意する動作にて直に判明する故、常に捕えて斬首その他の方法にて殺しつつあり、而して死骸は常に機関車内にて火葬す……」
こうして日本の「官」は極東全域にわたる戦略のもとに、いわば「土足」でシベリアに侵入し、数数の悲劇の種子をまいた。そして、ほとんどなにものも得ることなく、一九二二年に撤兵したのである。日本軍の死者約三千、凍傷を含む負傷者はその数倍にのぼり、当時装備や訓練で日本軍に劣っていたシベリアの革命軍側の死傷者は日本側の何倍にものぼったことは言うまでもない。人口の少なかったシベリアのことだけに、その傷痕は深刻であった。この「シベリア出兵」の記憶はシベリアのロシア人の問に長く残り、東部シベリアの各地に当時の戦死者の記念碑が建てられている。(P107,P108)
本書は、著者自身のシベリア抑留体験に多くのページが割かれている。著者は下級将校で、抑留中は肉体労働を行っているが、この点に関して以下の記述があり、労働を拒否すればできたが、それをしなかったことが分かる。 「反動」と称せられるグループは別にいたのである(その人たちがほんとうの「反動」かどうかは別にして)。彼らの多くは高級将校または警察畑の高官であった人たちで、自分の意志で労働を拒否していた。国際条約によって、将校は労働を拒否すれば拒否できたのだ。「反動」になれるほどの人は、健康であっても労働を拒否できる強い意志をもっていたし、逆にまた労働を拒否する人は「反動」とみなされた。しかしわたしを含む下級将校の多くは労働を拒否しなかった。わたしは、将校のはしくれとして、ときとして「吊るしあげ」の的になることはあったけれども、収容所での「民主運動」に敵意を抱いたことはなかった。(P23)
著者のシベリア抑留体験では、ショッキングな記述がある。(P192〜P200)
著者ら60人が伐採作業に従事していた時、日本人捕虜三人が脱走した。二人が一人をそそのかして脱走したものであったが、二人は逃亡途中にそそのかした一人を殺害して食料としたことが判明した。同胞を殺害して食料とする日本人は、日本人捕虜の中でも少数だろうが、それにしても、おぞましい事件に著者は遭遇したものだ。
最終更新 2022.2
北方領土関連書籍のページへ 竹島関連書籍のページへ 尖閣関連書籍のページへ
北方領土問題のページへ やさしい北方領土の話へ 竹島問題のページへ 尖閣問題のページへ
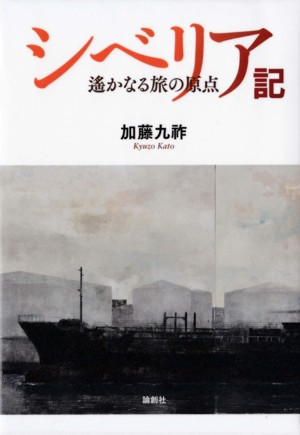 著者の故・加藤九祚先生は、国立民族学博物館教授などを務めた、文化人類学者で、日本のシベリア・中央アジア研究の基礎をつくった人。2016年、ウズベキスタンで発掘調査中に倒れ、現地の病院で死去した。シベリア抑留の経験があり、この関係でシベリア研究者となった。
著者の故・加藤九祚先生は、国立民族学博物館教授などを務めた、文化人類学者で、日本のシベリア・中央アジア研究の基礎をつくった人。2016年、ウズベキスタンで発掘調査中に倒れ、現地の病院で死去した。シベリア抑留の経験があり、この関係でシベリア研究者となった。